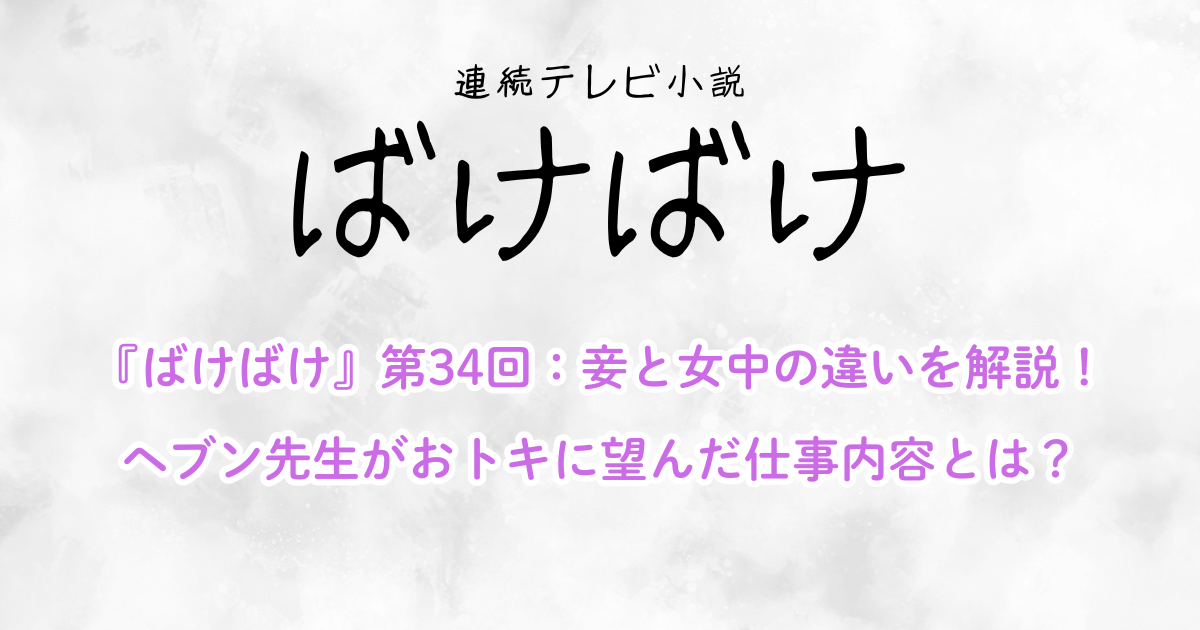NHK朝ドラ『ばけばけ』第34回では「妾(めかけ)」と「女中(じょちゅう)」に関して大きな誤解が生じるシーンがあり話題になりました。
そもそも江戸時代から明治時代にかけて、「妾」と「女中」とはどのような違いがあったのでしょうか?
本記事では、
『ばけばけ』第34回:妾と女中の違いを解説!ヘブン先生がおトキに望んだ仕事内容とは?
と題し、このドラマの史実の背景にある小泉八雲とセツの関係から紐解き、当時の女性の立場や仕事内容について徹底解説します。
『ばけばけ』第34回で起きた大きな誤解の背景
『ばけばけ』第7週・34回の放送で、おトキの父・司之介と祖父・勘右衛門は、月給20円という高額な給与から、娘が妾として働くことになったと思い込み激怒してしまいます。
しかし、ヘブン先生本人は「妾ではない!女中です」と、誤解を必死に否定します。
この誤解の裏には、明治時代の日本における外国人と日本人女性の関係、そして当時の社会的偏見が深く関わっていました。
江戸時代から明治時代における「妾」と「女中」の定義
妾(めかけ)とは何か
江戸時代、妾は家の継承者を得るために男性が正妻の他に置く女性を指しました。
武家社会ではとくに重要で、正妻に男児が生まれない場合、妾を通じて男系子孫を得ることが奨励されていました。
妾は奉公人の一種としてみなされ、金銭的なお手当を受けていたとされています。
妾の生んだ子が家の当主となることもあり、法的にも妾は妻と同じ夫の2親等として扱われていました。
一方、江戸中期以降には経済状況の変化に伴い、下級武士や一般商人の間でも妾を囲う習慣が広がります。
明治時代には法的地位は認められつつも、複雑な身分制度の中で妾は社会的に微妙な立場にありました。
女中(じょちゅう)と下女(げじょ)について
女中や下女は、武家屋敷や大商人の家で働く使用人を指しました。
彼女たちの仕事は炊事・掃除・主人や上主人の使い走りなど、いわゆる家事全般。
女中は基本的に「賄い付きの住み込み」という雇用形態で、給与はごく限定的でした。
当時、東京での機械織職(女性)の月給が2円60銭、小学校教員の初任給が5円だったことと比べると、女中の給与はそれより低かったのが一般的です。
女中には階級があり、御目見以上の奥女中から最下級の下女まで存在しました。
大奥での奉公は特に女性たちの憧れの職場でしたが、これはのちに娘の嫁入りの条件が良くなるという現実的な理由によるものでした。
明治時代における「ラシャメン」と外国人家庭の女性
ラシャメンという言葉の意味と差別
『ばけばけの』中でも度々登場する言葉「ラシャメン」。
「ラシャメン」とは、外国人と親密な関係にある日本人女性を指す言葉で、明治時代には強い差別と偏見の対象でした。
当初は外国人専用の遊郭で働く遊女や妾を指していましたが、やがて異人館に通う一般女性や外国人家庭の使用人、さらには外国人の妻にまで適用されるようになったのです。
この差別が生まれた背景には、外国人への根強い偏見に加えて、経済的格差がありました。
お雇い外国人は日本人の数倍の報酬を受けており、社会的な不満の対象でした。
たとえば、英語教師として松江に赴任したラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の年俸は100円。
これは県知事に次ぐ高額でした。
当時、三食付きの旅館宿泊費が1日30銭だったことからも、その待遇の良さがうかがえます。
外国人家庭で働く女性への社会的圧力
当時、外国人の家で働く日本人女性は「ラシャメン」と呼ばれ、社会的に貶められていました。
ドラマでおトキが「ラシャメンは世間から冷たい目で見られ、石を投げられることもある」と遊女のなみに聞かされるシーンは、当時の現実をよく表現していると言えるでしょう。
おトキが受け取った月給20円がかなりの高額だったゆえに、家族から「過酷な仕事=妾としての対価」と見なされてしまったのです。
ヘブン先生がおトキに対して望んだ仕事内容とは
実在の小泉八雲とセツの関係から読み解く
ドラマのヘブン先生のモデルとなったラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は、1891年2月ごろに松江で小泉セツを住み込み女中として雇いました。
当時39歳の八雲は、日本語がほとんど話せず、生活面での支援が急務でした。
一方、セツは父の急死と家業倒産により生活が困窮しており、知人の紹介で八雲の家に住み込むことになったのです。
ハーン自身は金銭感覚に無頓着な人物でした。
セツは後年の手記『思い出の記』で、「ヘルンは性来、金には無頓着の方で、それはそれはおかしいようでした」と記しています。
気に入ったものなら相場の何倍もの値段を出す人だったとも述べています。
月15~20円の給与を女中に支払ったのは、セツの仕事の価値を正当に評価したというより、単純に生活のサポートを重く見積もっての金銭感覚だった可能性が高そうです。
ハーンが本当に求めていたもの
ハーンが求めていたのは身の回りの世話をしてくれる使用人というより、日本の生活や文化を教えてくれるアシスタント、さらには心の通じ合う伴侶でした。
ハーンとセツの関係は単なる雇用関係ではなく、心を通わせたパートナー的なものに急速に発展していったそうです。
のちにセツはハーン『怪談』などの創作における語り部となりました。
日本の民話や怪談をハーンに話して聞かせることで、その再話文学を支えたのです。
「この本、みなあなたのおかげで生まれた本です。世界で一番良きママさん」というセツに対するハーンの言葉。
この言葉に代表されるように、セツは単なる女中ではなく、作品創作の重要なアシスタント兼人生のパートナーとして認識されていました。
『ばけばけ』におけるヘブンとトキの関係も、そのうような深い関係になることは間違いないでしょう。
「ラシャメンではない」と必死に否定した意味
ドラマで「オトキサン、ラシャメン、チガイマス!」と日本語で必至に訴えるヘブン先生の姿。
それは、当時の社会的偏見への怒りと、おトキに対する人間的な敬意を示す場面です。
社会的な圧力によって、セツとの関係を「妾」と見なされることをハーンは強く否定しました。
1896年2月、ハーンはセツの戸籍に入夫する形で正式に結婚し、自らも日本人として帰化しています。
これは西洋人としての身分を捨ててまでして、セツとの関係を社会的に正当なものにしようとした行動だったのでしょう。
明治時代の女性たちの選択肢と生存戦略
限定された選択肢の中での決断
ドラマ『ばけばけ』で描かれるおトキの状況は、当時の女性たちが直面していた現実の縮図です。
家族と実母と弟の生活を助けるために、社会的な差別を覚悟で外国人の家に女中として入る——このような決断は、当時の多くの女性たちが余儀なくされていました。
女性が生きるための職業は限定的で、結婚するか身を売るか、あるいは家族のために自分を売るしかなかったのです。
社会が偏見を持った理由
当時、外国人と関わりのある女性が社会的に貶められた理由。そこには、単なる道徳的非難ではなく、複雑な経済的・文化的背景がありました。
高い給与を得ることで派手な装いや高級な装飾品を身につけることができた女性たちは、日本人相手の遊女とは異なる存在として一目で判別されました。
こうした経済的格差に対するねたみも「ラシャメン」への差別意識をさらに強めていったと考えられています。
『ばけばけ』第34回から読み取れる歴史的背景の重要性
『ばけばけ』が第34回で描き出したのは、
明治日本における外国人受け入れの困難さ、
女性の社会的立場の複雑さ、
そして、社会的偏見がいかに個人の人生を左右するかという深刻なテーマです。
ヘブン先生の「ダキタクナイ」という言葉による誤解から、その後の説明と爆笑シーンへと至る流れは、当時の社会的背景を理解することなしには、ドラマの真の意味を見失うことになります。
史実の小泉八雲とセツの関係を知ることで、『ばけばけ』がなぜこのシーンを含めたのか、そしてその重要性がより一層明確になるでしょう。
まとめ:『ばけばけ』第34回:妾と女中の違いを解説!
『ばけばけ』第34回で描かれた、ヘブンに対するおトキと松野家の誤解。
それは、明治時代における「妾」と「女中」の社会的立場の違い、外国人に関わる女性への根深い偏見、そして当時の女性たちが限定的な選択肢の中で生きていかざるを得なかった現実をも浮き彫りにします。
ヘブン先生が「ラシャメン、チガイマス」と必死に訴えるシーンは、単なるコミカルな展開ではなく、当時の社会的差別構造への抵抗を表現したものです。
史実の小泉八雲とセツが経験した100年以上前の日本社会の課題は、ドラマを通じて現代を生きる私たちにも深い問いを投げかけています。
明治時代の日本社会構造を理解することで、ドラマの感動がより一層深まるでしょう。
『ばけばけ』関連記事はこちら